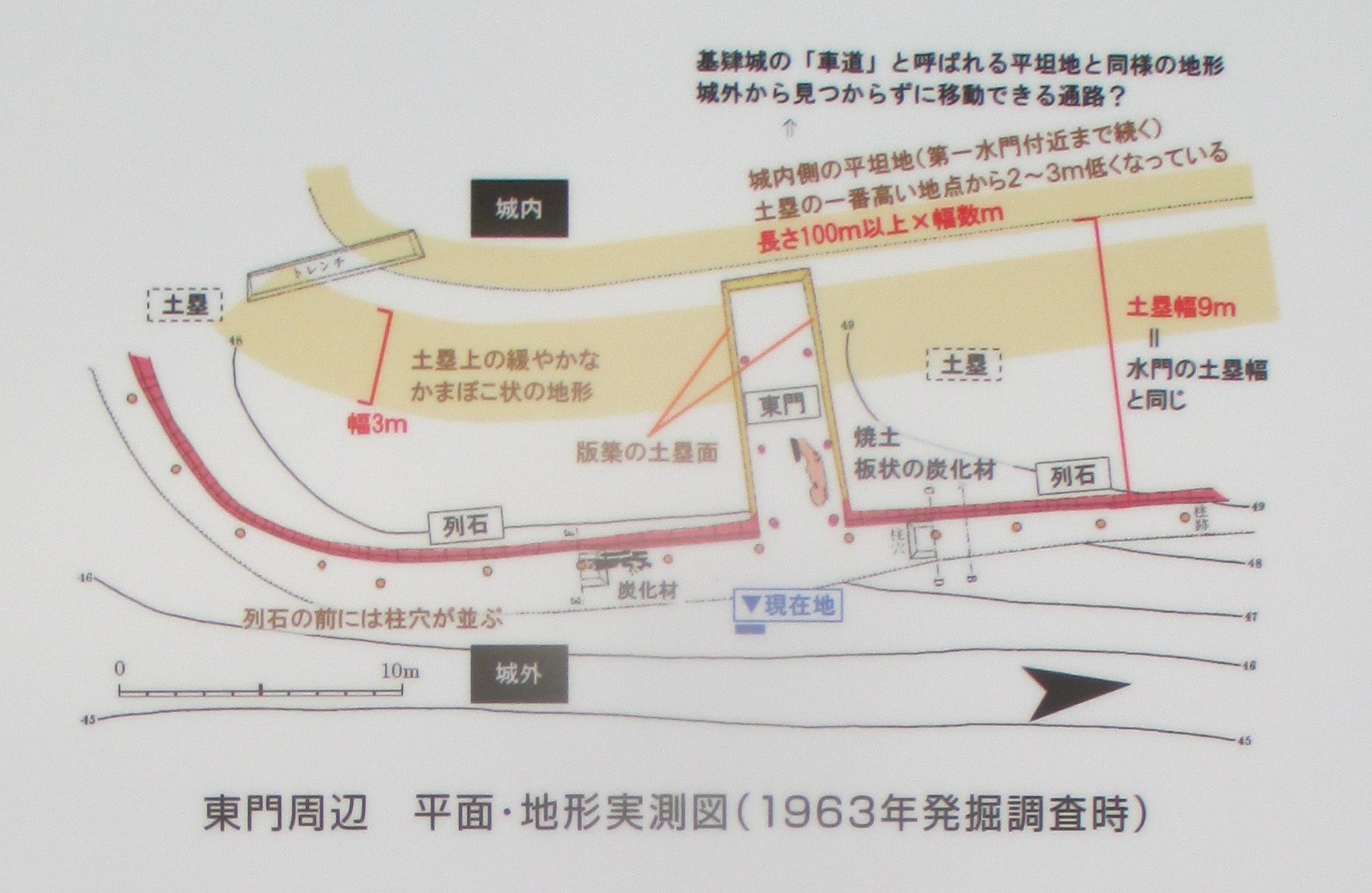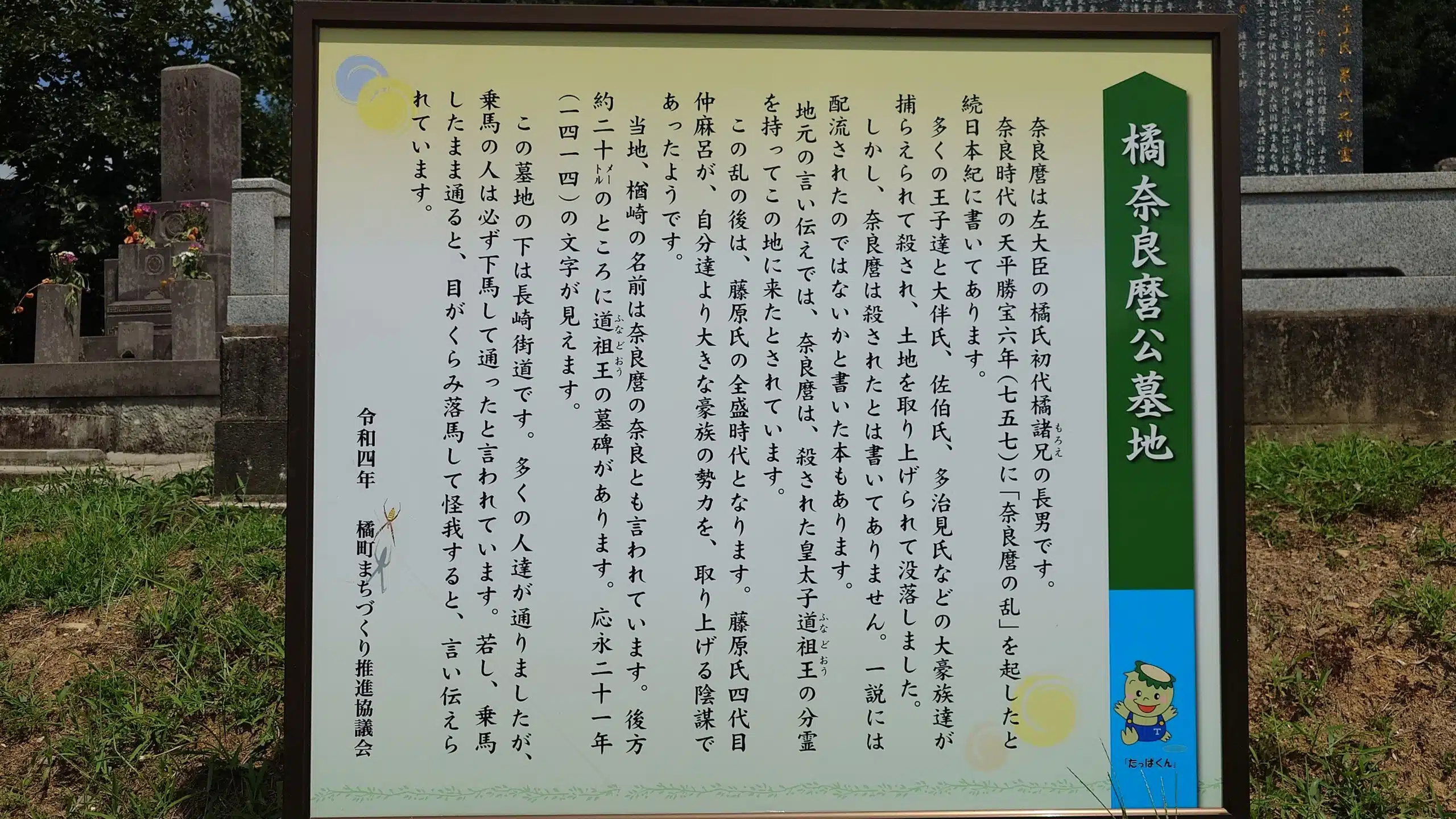下記解説のついては、『郷土史 橘町史跡めぐり』橘町歴史研究会 編 P242 より引用しています。
孝女の籬(まがき)墓碑(中村静夫氏所有地にある)
更に南側台地の尾根を進むと、山林の中に孝女籬の墓碑がある。 は文化年間(江戸時代1804年~1817年)の人で貧しい小作農の家に生まれ、病床の父母によく孝養をつくした。
文化11年(1814年) 朝廷において全国の孝子、節婦義僕等を表彰された時、は孝子として表彰の栄に浴した。当時の佐賀本藩藩主鍋島治茂は特に籬のため「孝子伝」を著し、広く世に紹介された。
墓碑は高さ3mにも及ぶ立派な石碑で、の顕彰文も刻んであるが風化が進んで読みにくい。(文中藤津郡楢崎村という言葉がある。文化のころ楢崎村は藤津郡に属していた)
この墓碑は大正12年3月15日学制発布50周年の記念事業で建立されたものである。(当時橘小学校校長山口良吾氏)

時代的には江戸時代後期の碑です。

ここをクリックすれば残りの記事が読めます。
孝女籬について(孝女伝より)(原文は、漢文調の美文ですが、平易に意訳させていただきました。)
文化の頃、藤津郡楢崎村(現在は武雄市橘町南楢崎)に弥右衛門と言う百姓がいた。他人の田畑を小作して僅かに生計を立てていたが、勤勉家でもない上に夫婦揃って大の酒好きであったからいつも貧乏であった。近所の人からも「飲右衛門」と言われ嫌われ者であった。
ところが「鳶が鷹を生んだ」とでも言うのであろうか弥右衛門夫婦の間に擁と言う孝行の一人娘があった。籬は人の十倍も孝行娘で、そのうえ千人に一人も居ない程の美人であった。家が貧しかったので幼少の頃から糸を紡ぎ機を織って父母の酒代の足しにしていた。しかし、運命の魔神はその位では許さなかった。縮が十才になった時、母が突然血暈症にかかり、病床に臥したのである。籬の心配はそれこそ大変であった。それ以来、縮はか弱い細腕で一家の生計を支えた。 或る時は他人の着物を洗濯し、或る時は荒れた田畑を耕して親子が何とか食べていけるように働いた。 籬は苦しい生計の中から両親の好き酒を用意することを一日も忘れなかった。そして、両親が喜んで酒を飲んでくれるのを見て一日の疲労を忘れ、神に感謝するのであった。しかし、籬の一日はまだ終りません。帯を解く間もなく、病床の母を看病し、一晩中按摩して夜を明かす日があった。母の病が悪化すると、賃仕事に出ないで看病した。
すると早速困るのが酒代です。 は事情を酒屋に話し酒を借りて両親にすすめた。籬は酒代を払うために僅かの時間を惜しんで今までにも増して働いた。
籬が19才になった時、結婚話があった。しかし「自分が他家に嫁ぐことになれば自分だけは幸せに暮せても父母の世話は誰がするでしょうか。自分の他に誰も世話する者はありません。」籬はこう言って涙を流して結婚の話を断った。籬も娘盛りである。 誰が好んで花を咲かせないはかない生活を選ぶ者が居りましょうか。前は自分の運命の悲しい境遇を考え、人の妻になることのかなわないことを覚悟していたのである。人間の悲哀もこれ程までの痛切を極める境遇になれば、宿命と諦め、深い沈黙と尊い犠牲の中に一筋の光明のさすことを願う外はなかった。
こうしては結婚できない悲しみを秘め、酒好きの父につくし、病床に苦しむ母の看病、一家の生計を支えるための過酷な労働と四重苦に耐え、ただひたすら努力を続けていくのでした。
文化年中、朝廷におかれては有司に命じて、日本全国の孝子、 節婦義僕を調査し表彰された。その折に孝子離も有司に認められ役人に招かれて、いろいろとご下問があった。
役人「あなたが父母に孝行をつくしている様子を話して下さい。」
籬 「私は孝行とはどんなことかよく知りません。」
役人「あなたが父母のお世話をしている様子を話して下さい。」
籬 「私の家は貧しくて、朝は今日一日どうして暮そうかと心配ですが、一生けん命働いて何とか一日一日を食べていっております。夕方になって今日一日生きられたことを喜び、朝は一夜無事に過せたことを喜び、毎朝天を拝みながら大きな自然のご恩を有難く思い、何とかこのご恩に報いたいと考えるだけでございます。朝から両親はお酒を喜んで飲みます。私はそれを見て疲れを忘れ、毎日の酒代をかせぐため一生懸命です。さびしいとも思いません。」
役人ととの問答はこのようでした。
無学で一字も知らず、孝行はどんなことか説明することも出来ないですが、毎日毎日の姿は最高の孝行だと云うことのできる籬です。 世の中では賢婦烈婦の本を読み、人間としての立派な行について書かれ書物を読むことの出来る知識人が、かえって父母や姑をさげずみおごり高ぶる人がいます。この新風の女性と比較して見る時、その差はどれ程でありましょうか。
本当にけ高い花は荒野に咲いて人に眺められずに散ってしまい、美しく輝く珊瑚は海底にあって世の人々に認められずに終ることの多い世の中です。
この度の朝廷の孝子節婦の表彰はただ僅かに賞品や賞金賞詞を与えられたに過ぎませんが、この美しいの孝順は時の藩主(佐賀本藩第8代明和7年 1770より文化2年 1805)鍋島治茂の著された「孝子伝」と共にいつまでも美談として後世の人を教え、発憤させ、善導して行くでありましょう。
(以上孝子籬については南楢崎区の故中村静夫氏より取材)