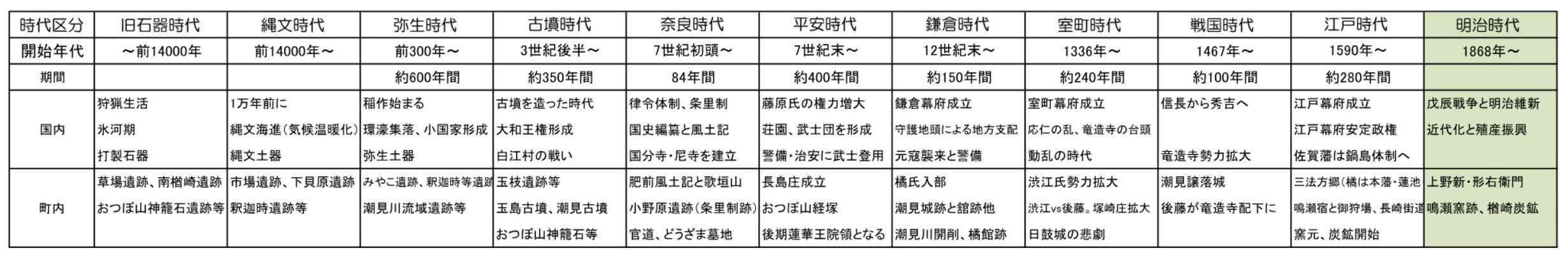下記解説のついては、『郷土史 橘町史跡めぐり』橘町歴史研究会 編 P172 より引用しています。
八郎社(八郎さん)
源八郎為朝の遺跡としては、おつぼ山の頂上に「八郎さん」と称する為朝をお祭りした神祠がある。観音開きの戸のある石祠で文字は何も見えない。
9月1日は八郎さんの祇園である。当日はおつぼ山山頂の祠一帯を清掃し、潮見神社から御幣をいただいて神前に供え、祭事を行う。この地区若者の手で鐘や太鼓を頂上まで運び上げ神前に浮立を奉納する。ここの山道は急坂でただ登るだけでも苦しいのに、神に奉仕しようとする若者の純真な気持がこのような祭を遂行するのであろう。後は天神さんの境内で夜遅くまで浮立をする。
今はおつぼ山の頂上は檜の造林が行われ、展望がきかないが、昔八郎為朝は「この頂上から弓を射て黒髪山の大蛇を退治した」と云う話が語り伝えられている(中村常雄氏の話 おつぼ山~黒髪山 距離10㎞)
ここをクリックすれば全文を読めます
小野原と源八郎為朝とはどんな関係があったのか
為朝は源為義の子で、九州に下向したので鎮西八郎為朝とも呼んだ。乱行が多く父為義を大変困らせた。為朝の乱行によって父為義は官を解かれたこともあった。(久寿元年)
保元の乱(一二五五年 保元元年)では為朝は院方に属し、敗れたので父や平忠正は斬られたが為朝は若年のため伊豆大島に流され助かっている。保元の乱の前々年(久寿元年 一二五四年)朝廷は太宰府に命じ鎮西の諸勢力は為朝に助力することを禁じている。当時為朝は九州に下向していたのである。
武雄市では、為朝が若木町に舘を造り居住したという言い伝えがある。自分の舘を御所(天皇の御所になぞらえた。今は地区の名前になっている)と呼ばせた。また、弓かけの松の伝説も残っている。
中村常雄氏(元小野原区長)によると為朝はその頃、小野原にも来ておつぼ山の頂上に城を築いたと云うことである。おつぽ山はその昔神籠石が築かれた所で水も豊富であり、城を築く場所としては絶好の場所であったと思われる。こう言ったことで村人とも親しく交わったのではないだろうか。
このような関係でおつぼ山の頂上に「八郎さん」として祭られたらしい。この城との関係で北楢崎の入口(県道よりの分岐点付近)を今も城口(ジョウグチ)と呼んでいる。









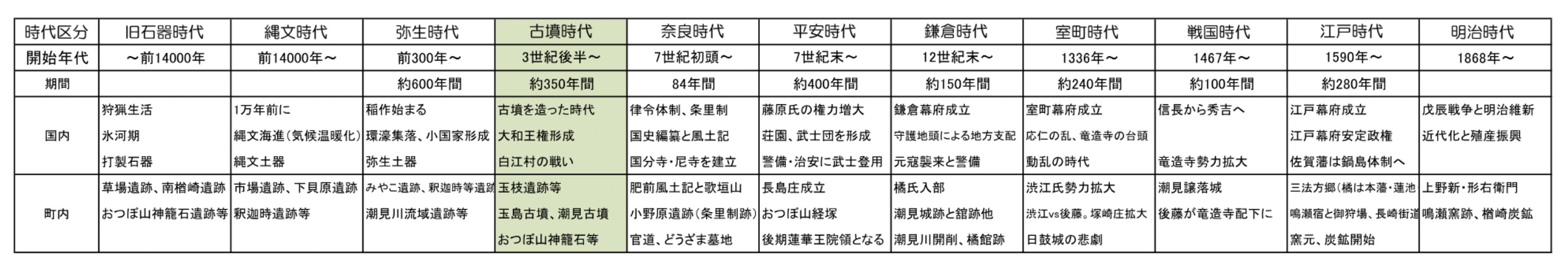



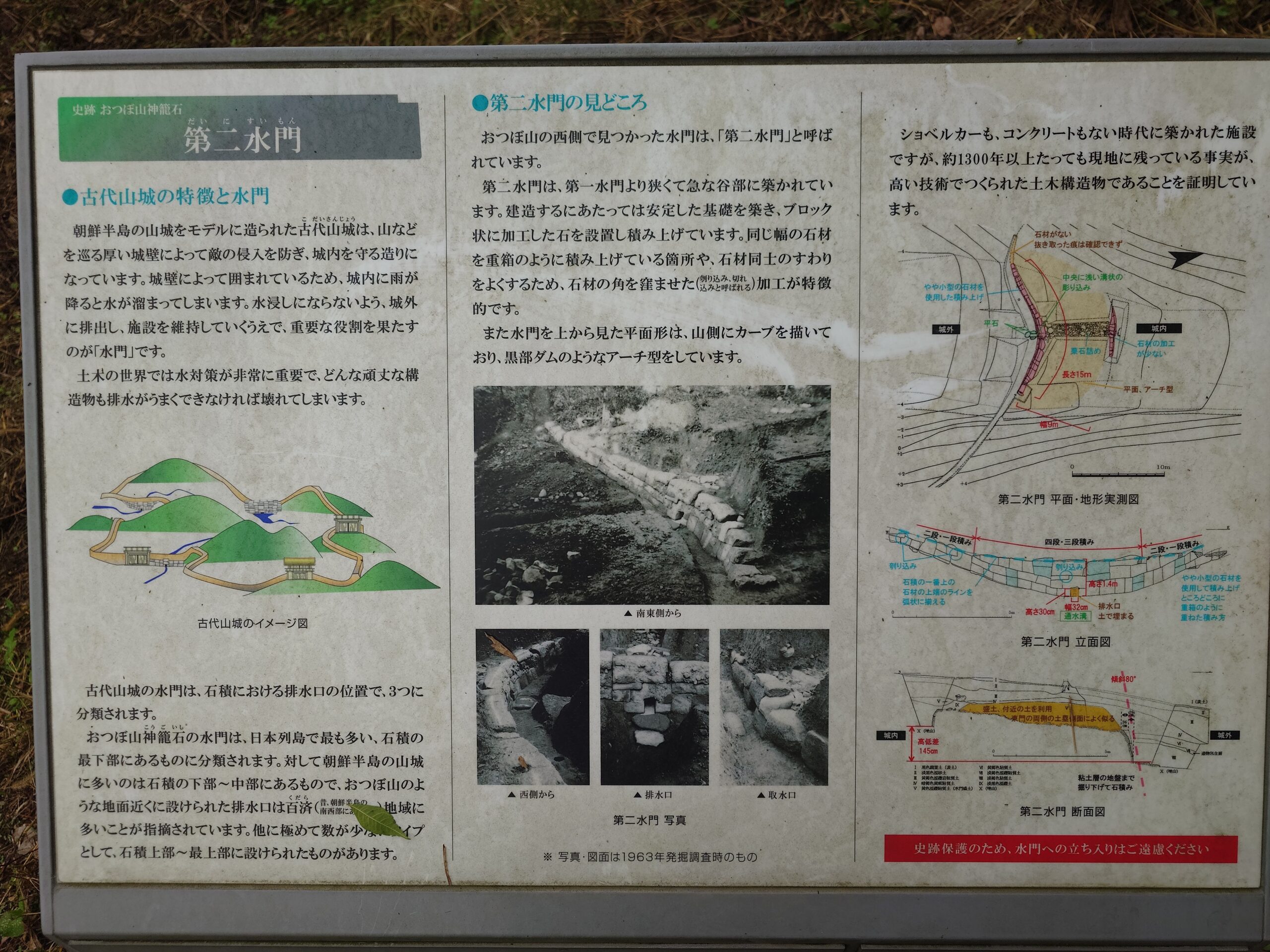

写真大甕は4石甕-scaled.jpg.webp)