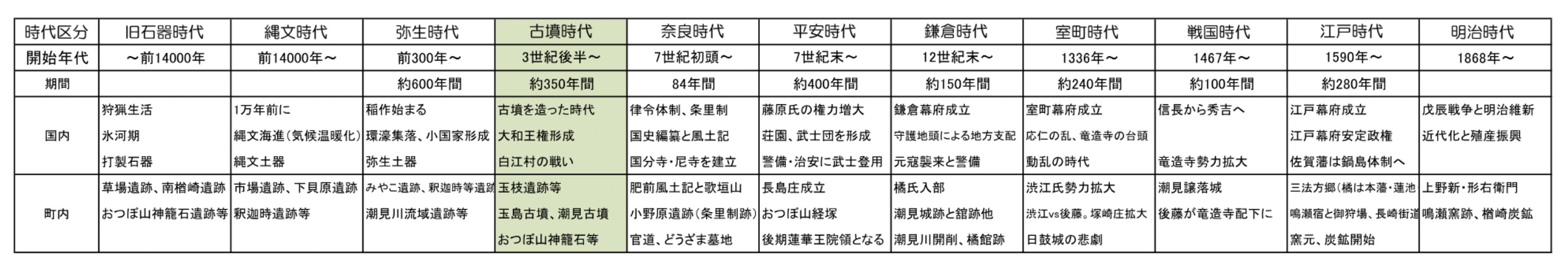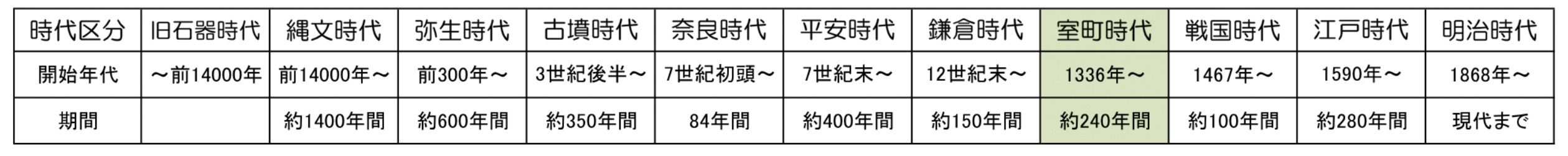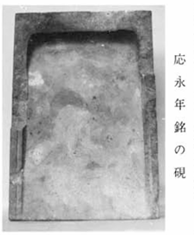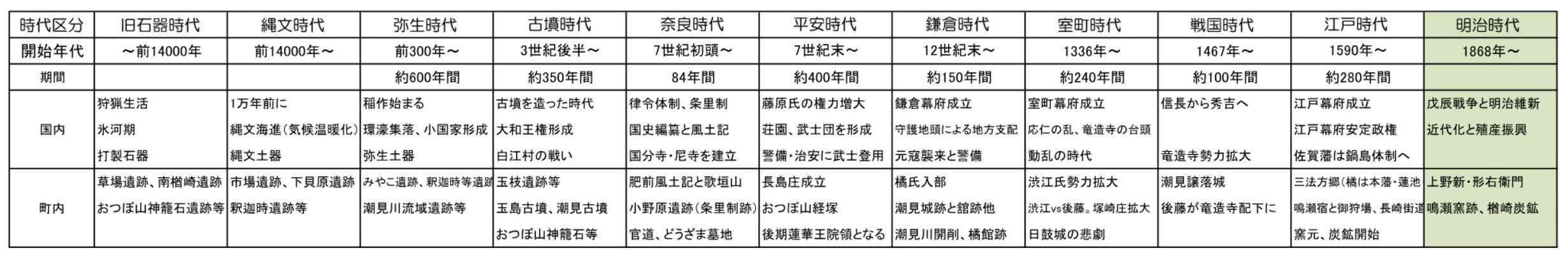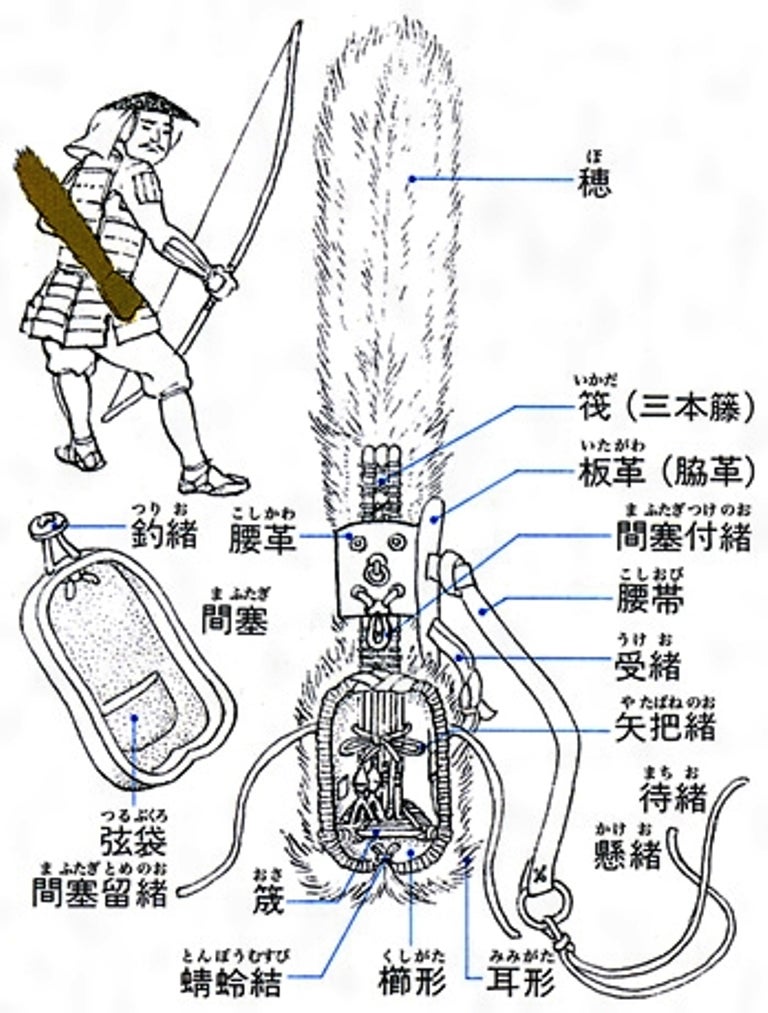今から1300年以上前に造られた朝鮮式山城です。学者の間で神籠石が神様をまつる場所なのか、山城なのかが長らく議論されていましたが、山城だと初めて明らかにされたことで有名です。国史跡に指定されました。
663年の白村江の戦いの後、防御施設として造られた可能性が高く、約1.9㎞の列石(一部欠落)、アーチ状の第1・第2水門、東門、版築構造(図のように土を突き固めて作る工法)の第1土塁などがよく残り、立岩立岩付近が列石の原材料地と考えられます。
参照:㊹ おつぼ山神籠石 詳細解説
参照:橘町のみどころより 歴史シリーズ④ おつぼ山神籠石
参照:武雄市の文化財 おつぼ山神籠石のパンプレット
参照:おつぼ山神籠石 第一水門・南門
参照:おつぼ山神籠石 第二水門
参照:おつぼ山神籠石 東門
時代的には古墳時代の遺跡です。




下記 ▶豆知識 をクリックすると内容を表示します。
↓
豆知識 神籠石(こうごいし)
神籠石は、北部九州を中心に瀬戸内地方にかけて分布する、山に築かれた古代の城跡である「神籠石(こうごいし)式山城」を指す遺構の総称です。特徴は、山中の尾根や谷を幾つか取り込み、外周に土塁を巡らせ、その土塁の根元に切石を並べた列石で囲いを作っている点です。山城の存在は確認されているものの、日本書紀などの古い文献に記載がないため、その目的や築城背景については未だ多くの謎に包まれています。
参照:神籠石(Wikipediaへ)
神籠石の主な特徴
-
古代山城の一種:山の尾根と谷を取り込んで築かれた大規模な構造を持つ古代の山城です。
-
列石と土塁:築城された土塁の基底部に、方形状に加工した切石を並べた列石が見られるのが特徴です。
-
水門の存在:谷筋には、水が通るための水門が設けられています。
-
文献に記載がない:『日本書紀』などの正史に記録がないため、謎が多い遺構とされています。
-
築城時期の特定:一般的に白村江の戦い(663年)以降の7世紀後半に、大陸からの脅威に備えて築かれたと考えられています。
Google AIによる概要 より
豆知識 白村江の戦い(はくそんこうのたたかい、はくすきのえのたたかい)
白村江の戦いは、663年に朝鮮半島・白村江(現在の錦江河口付近)で、百済復興を目指す日本・百済連合軍と、唐・新羅連合軍の間で行われた海戦です。日本は唐・新羅連合軍に大敗し、百済は滅亡、日本は朝鮮半島への影響力を失うことになりました。
詳細:
- 背景
660年に百済が唐・新羅の連合軍に滅ぼされた後、百済の遺臣たちは日本に救援を求め、日本は百済復興を支援するために出兵しました。 - 戦闘
663年8月27日、白村江で日本・百済連合軍と唐・新羅連合軍が激突。日本は水軍を主力として戦いましたが、唐・新羅連合軍に大敗しました。
- 結果
日本は百済への影響力を失い、朝鮮半島から撤退せざるを得なくなりました。この敗戦は、日本にとって大きな転換点となり、国内の整備や律令国家の形成に力を入れるきっかけとなりました。
- 影響
白村江の戦いは、日本が初めて経験した本格的な対外戦争であり、その敗北は日本に大きな衝撃を与えました。この経験から、日本は国防意識を高め、大宰府の防備を固めたり、烽(のろし)や水城(みずき)を設置したりするなど、様々な対策を講じました。
Google AIによる概要 より
編集:橘町歴史研究会 宮下