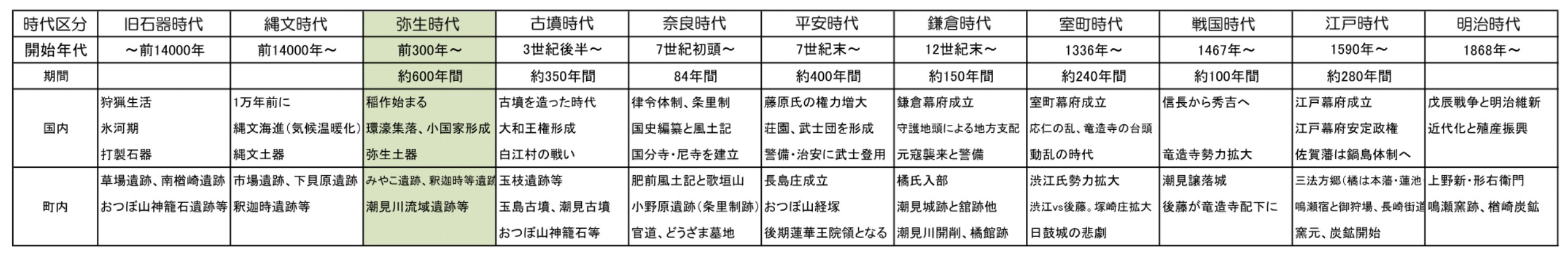弥生時代(今から2千年以上前)の甕棺と石蓋石棺墓が見つかっています。「道路にあるため 露出している甕棺はほとんど破損しているが 須玖式のもので、石蓋甕棺も存在していたことが知られる。この甕棺の埋蔵範囲は明らかでない。」(佐賀県文化財13 p438)と書かれています。
古代東川と潮見川は、この一帯で合流して大きな川となり、縄文海進の頃には河口であったと考えられます。当時の人々は、ここから東の山麓一帯に狩猟や漁をしながら暮らしていたと考えられます。
参照:橘町の見どころ 歴史シリーズ ⑩
参照:橘町の見どころ 歴史シリーズ ⑪
参照:橘町の見どころ 歴史シリーズ ㉒
時代的には弥生時代の遺跡です。

杵島山麓の小河川と縄文遺跡

石蓋石棺墓の例(吉野ヶ里遺跡より)

草場橋からおつぼ山南麓遺跡
下記 ▶豆知識 をクリックすると内容を表示します。
↓
豆知識 須玖式土器(すぐしきどき)
須玖式土器は、弥生時代中期、特に北部九州に分布した、赤く磨き上げた丹塗磨研土器(にぬりまけんとき)を代表とする弥生土器の一種です。特徴は、文様をほとんど持たない洗練されたシンプルな形状と、美しい磨き上げられた表面にあります。この土器は、祭祀などの非日常の場で使われたと考えられています。
Google AIによる概要 より
豆知識 縄文海進(じょうもんかいしん)
縄文海進とは、縄文時代に起こった、現在よりも海水面が高くなった現象です。約6000年前頃に最高潮を迎え、その時期には現在の海面より2~3m(有明海沿岸は最大約5m程度)ほど海水面が高かったと推定されています。この海水面の上昇により、本来の海岸線が内陸深くまで入り込み、広大な入り江や内湾が形成されました。
Google AIによる概要 より