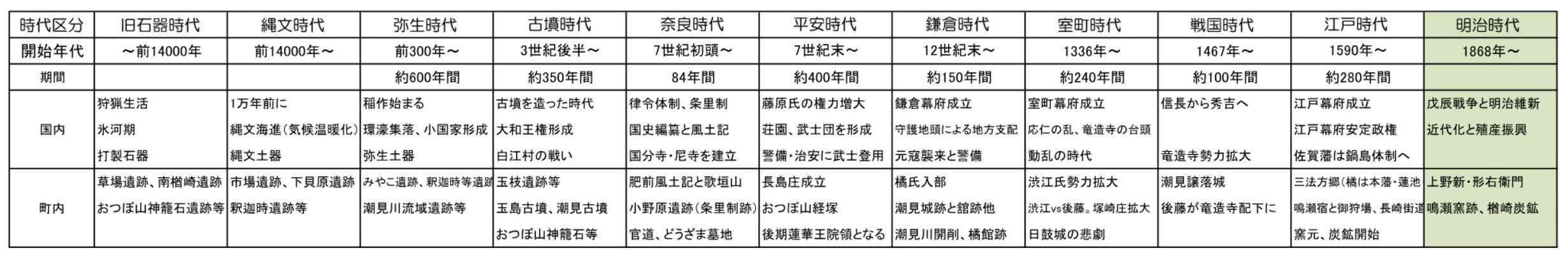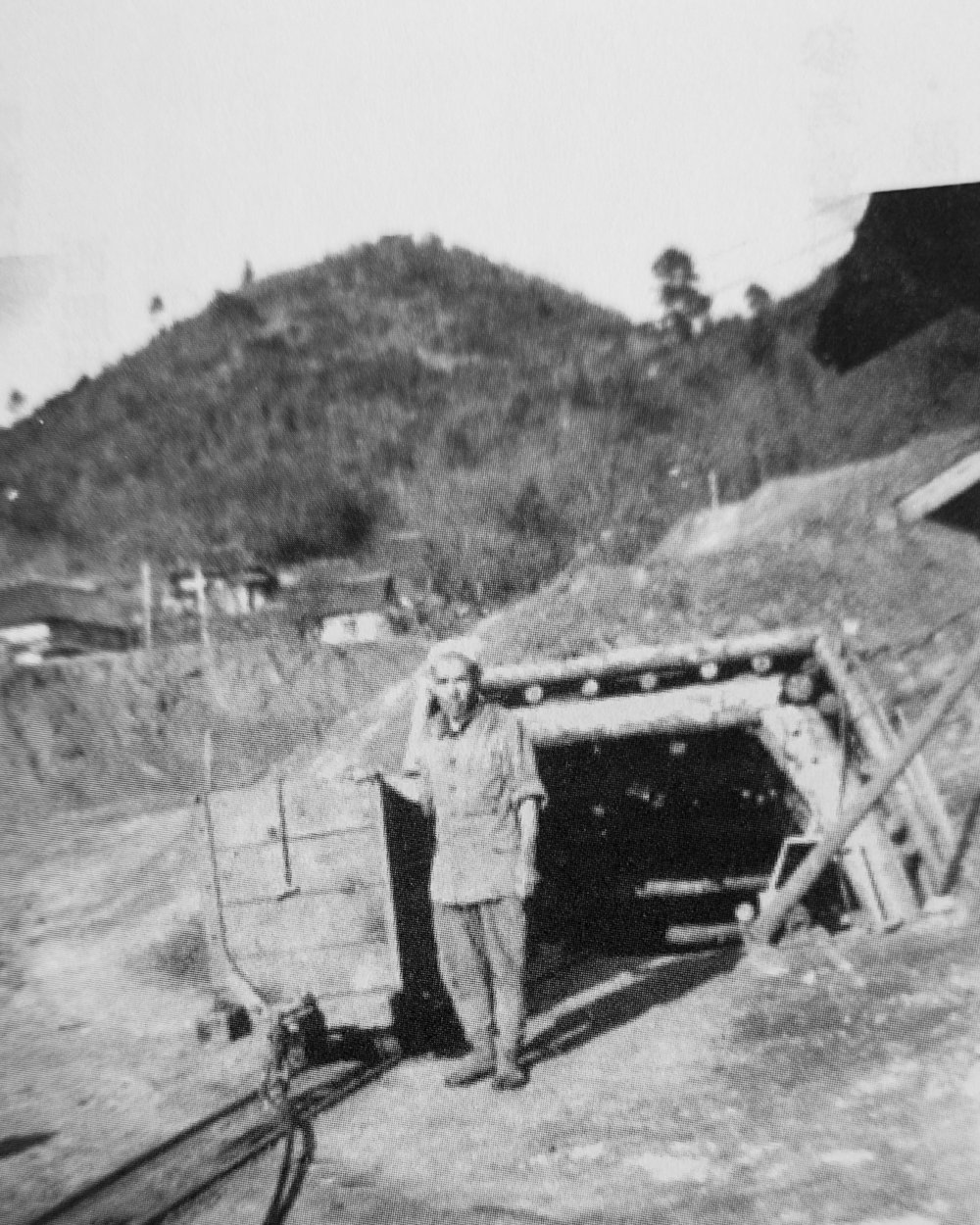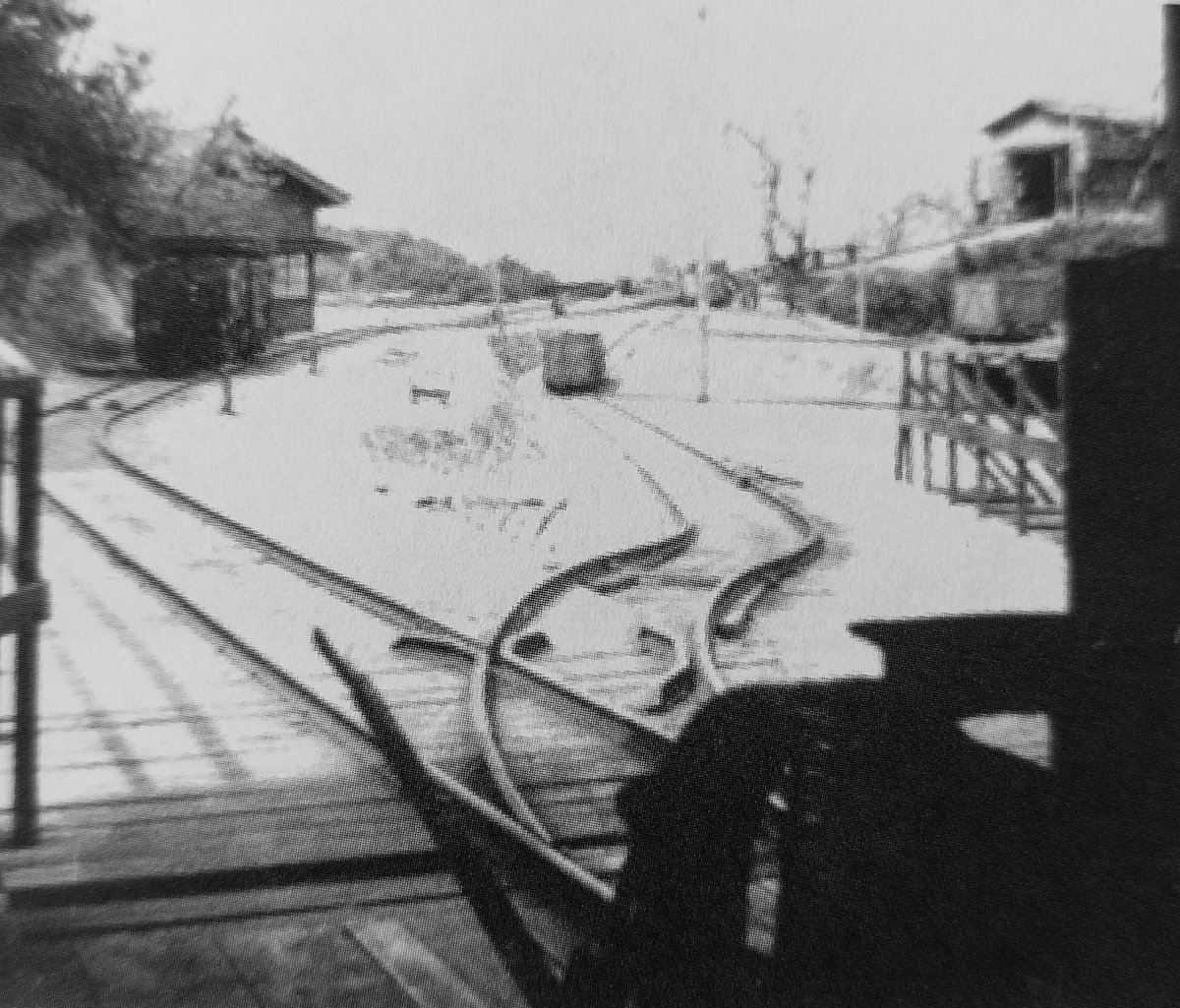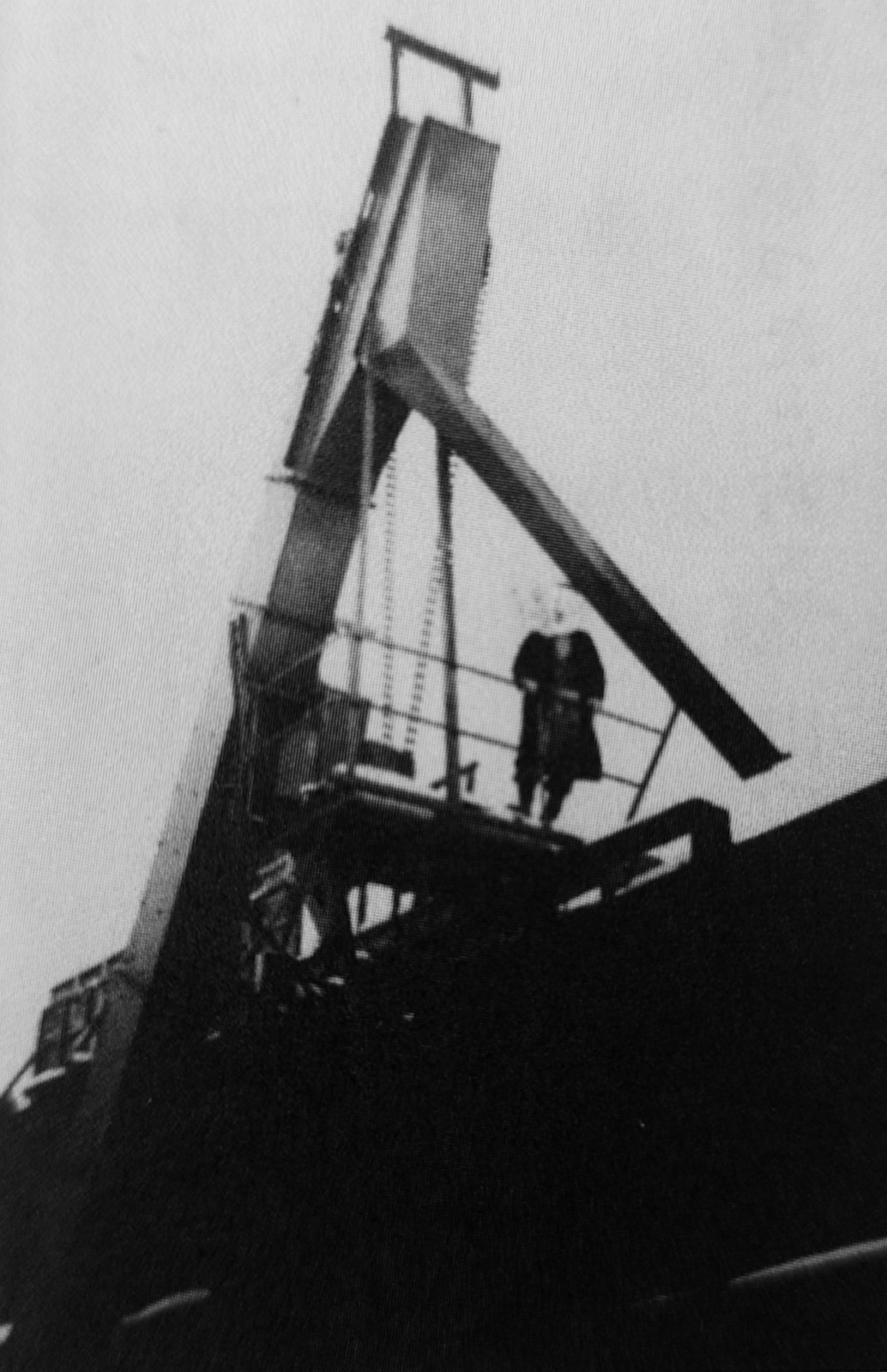橘町には、明治、昭和の時代に炭鉱がありました。
橘町の炭鉱について、橘町歴史研究会で平成31年出版された「橘町 近代・現代史」から紹介します。(項目を箇条書きに改め、出典を割愛しております)

南楢崎炭鉱跡に残る施設
目次
(1)初めに
-
- 炭鉱はなぜ「ヤマ」と呼ぶのか
- 佐賀県内の炭鉱の発展と衰退
(3)南楢崎 南楢崎炭鉱
(4)鳴瀬炭鉱
時代的には明治時代以降の史跡です。
ここをクリックして開きます
(1)初めに
- 炭鉱はなぜ「ヤマ」と呼ぶのか
日本書紀の中に、天智天皇の御代、越後国で「燃える石」が見つかったとある。山の上に雷が落ちて草木が燃え、石塊が黒煙を出していた。この石塊を家に持ち帰り燃料に用いたとある。山の上から持ち帰ったので、この石塊の在る場所を「ヤマ」と呼ぶようになった。 - 佐賀県内の炭鉱の発展と衰退
- 県内で一番早く発見されたのは、北波多村大字岸山の農夫が、享保年間(1716年~1735年)に発見した。
- 武雄市内では、花島村野間山で、 武雄鍋島家の直営事業として天保11年(1840年)開始されたと古文書に在る。
大口需要者は、小田志の窯焼溝上の湯屋・鳴瀬の風呂等と記す。 - 明治6年鉱山法令にて国有化になり、県内でも採炭許可を得る人が多く、小規模炭鉱が濫立して供給過剰となって経営困難となり、一時休止・閉山に追い込まれた。
- 其の後、蒸気機関車が導入されて需要が高まり、又、世界戦争のたびに盛衰を繰り返す中、石炭はエネルギー源の中心的役割をして発展してきた。
- しかし、昭和30年代になれば、エネルギー革命によって、石油・ガスへの転換となり、これが経営困難と成って、県内の炭鉱は昭和48年に全て姿を消した。
(2)北楢崎 南杵島炭鉱(リッキー炭鉱)
名称:市丸炭鉱
(市丸利吉・高治)
↓
新龍炭鉱
(市丸利治)親子三代続く
- 明治20年12月開口
市丸炭鉱 鉱主 山崎常右衛門 (石炭史より)と坑主 市丸利吉の共同経営から、経営を市丸氏へ譲る。 - 明治30年休止
- 大正5年再開
新龍炭鉱 鉱主 市丸利治 - 昭和28年頃閉山
坑口は上古賀(北楢崎区一班)→ 谷古賀(同二班)→ 中林(同三班)へと移る
石炭はトラックにて武雄駅へ運んでいた。
従業員は最大の時百数十人居たが、地元の人は少なかった。
炭鉱住宅が、 公民館南側に社宅として8棟と、中林・尾ノ上分岐道の両脇に2棟づつ在った。
写真1 神龍炭鉱-最後の坑口
写真2 社宅 溝を挟んで両側に2棟づつ建っていた
(3)南楢崎炭鉱
名称:貝島系大辻炭鉱橘鉱業所 (大辻炭鉱史より)
- 昭和27年11月開口
大辻炭鉱は、貝島炭鉱の所有する南楢崎と久間の採掘権を一千万円で購入して、起工式を行った。 - 昭和35年9月閉山
- 北九州の本社は、昭和40年廃山となった。
石炭の運搬はトラック2台で高橋駅まで運んでいた。
主に火力発電所で使用された。
従業員76名ほとんどが地元採用され、又、下請け (菅組・山崎組) は採炭と仕繰りを請け負っていた。
写真3 坑内から引き上げ、反転して置き場へ運ぶレール
写真4 チェンコンベアーと中塊炭ポケット(50トン入)
写真5 雪の坑口
(4)鳴瀬炭鉱
名称:西肥炭鉱
鉱主:鳥越甚太郎
(石炭史より)
- 大正8年開山
- 大正11年閉山
3ヶ所の坑口があった。
○ 旧道入口東の山麓
○ 天理教鳴瀬教会東の裏山
○ 旧道入口東の山麓から南へ約80mの所
経済状況・規模等不詳